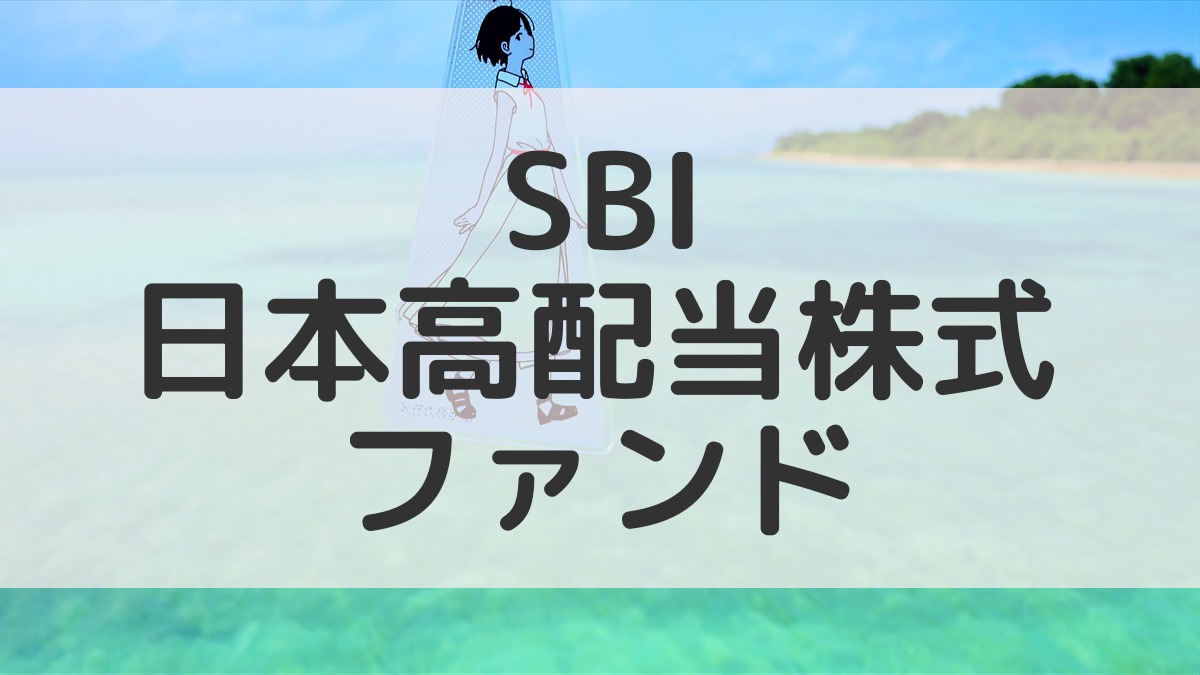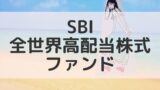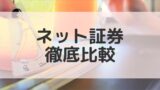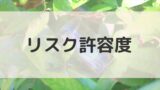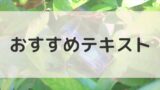2023年末から始まった、SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
配当もキャピタルゲインも狙うという、とても魅力的な投資信託です。
今回はこのファンドを、2025年10月31日付の月次レポートをもとにレビューしてみます。
なおこれらの記事は定期的に更新しています。
- いわゆる景気敏感株の保有割合が増えた。
- 構成銘柄数は101銘柄(前回95)と増え、まだまだ分散させていく可能性。
- 日銀の利上げによる恩恵を狙って、金融株の動向に期待している。
- 依然として94%が株式でハイリスクよりのファンドなので、買うなら少額積立が無難かも
- ただしベースとなる投資方針は設定から一貫している
直近の成績
期間収益率
過去1ヵ月:3.05%(前回調査時2025年2月は▲1.13%)
過去3ヵ月:11.91%(同3.89%)
過去6ヵ月:25.39%(同2.69%)
過去1年間:29.15%
設定来:49.53%(同19.32%)

設定来リターンはプラスで、前回調査時2025年2月よりもかなりパフォーマンスとなっています。
過去1ヵ月~1年の全期間で前回よりもよいリターンとなっています。
特に10月からの伸びは良好で、レポートでは「高市政権への期待」が一因とも書かれています。
分配金
2025年10月10日の決算日で、1万口あたり130円の配当が出ています。

しかし、今後のパフォーマンス次第では特別配当金となる可能性があります。
特別配当金は、要するに元本の払い戻しです。
つまり投資家の利益にならない配当金で、そのため課税もされません。
→ 分配金は2種類あるの? – 野村アセットマネジメント
ポートフォリオの状況
・株式組入比率 94.73%(前回調査時は94.2%)
・配当利回り 3.4%(同3.92%)
・PBR 1.94(同1.45倍)
・ROE 11.63%(同12.1%)
ファンドの運用状況(抜粋・要約)
- 10月はTOPIXが+6.19%となり、ファンドのパフォーマンスも+3.05と上昇した。
- 東京エレクトロン、フジクラなどがプラス寄与。
- 東京海上HD、第一生命HDなどがマイナス寄与。
- 新たに三井住友FG、富士電機を購入した。
- 株価上昇したフジクラのウエイトを下げ、エアウォーターを売却した。
10月のパフォーマンスは良かったようです。
しかし、高配当銘柄中心のファンドであるため、株価が急上昇したハイテク関連銘柄の恩恵にはあずかれなかったようです。
また今回は、不適切な会計処理が発覚したエアウォーターをバッサリと売却しています。
この損切りの大胆さを、私たち個人投資家もぜひ見習いたいものですね^^
なお組み入れ銘柄数は101銘柄となっており、2025年2月の95銘柄から増えました。
数ヵ月単位で見ると、徐々に銘柄数を増やしているようです。
今後の運用方針(抜粋・要約)
・10月は日経平均が歴史的な上昇となったが、半導体など日経平均の構成比率が高い銘柄の急上昇に追随しきれなかった。
・高市新政権の誕生によって日銀の利上げは先送りされているが、国内インフレ率が高止まりしていることから、日銀の利上げによる収益改善が見込まれる金融株は引き続き期待できると考えている。
・引き続き、収益性に優れ配当力のある企業への投資を行い、インカムゲインと中長期的なパフォーマンスにつなげたい。
前回まで毎回記載されていた、
・短期的には金融など特定セクターの銘柄を組み合わせることも考慮している。
・高配当利回り銘柄比率は高め、それ以外のウェイトは抑えめにしている。
・引き続き市場動向をモニターしつつ、適宜銘柄入替や投資比率の調整をしていく方針。
という方針は記載削除されています。
ベースの方針は変わらず、利上げの恩恵を受けられそうな金融株を注視しているようです。
構成銘柄・セクタ比率
銘柄数は101社、そのうち開示されているのは上位30社。
分散投資の有効性が出てくる70銘柄を越えているので、リスク分散も意識しているようです。(→分散投資とは?)
2月時点では95銘柄でした。数ヵ月かけても101銘柄なので、100銘柄付近で安定するのでしょうか。
各銘柄の保有比率は1~4%強となり、分散を利かせているようです。
1つの銘柄を極端に多く保有することはないようです。
銘柄比率上位のソフトバンク、SBIHDなどは継続してトップ10入りしています。
セクタ比率は、電気機器、銀行業、輸送用機器は引き続き上位をキープ。
ディフェンシブ銘柄である医薬品の比率は少し上がりました(14位→ 10位)
日銀の利上げを期待してか、意識的に銀行業を保有しているようです。
(→ディフェンシブ銘柄とは?)
※▼リストはタップすると拡大します。

ファンドの基本情報
ファンド特色
高水準のインカムゲインと中長期的なキャピタルゲインによるトータルリターンを追求する。
基本的には、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄選定・投資比率決定を行う。
…配当も値上がり益も狙うとはなんて欲張りな投資方針なんでしょう笑
でも、こういったわかりやすく欲丸出しのファンドは今まで目立たなかったので、その潔さが人気の秘訣かもしれません。
ファンド設定後わずか48営業日で、純資産総額が500億円を突破したことからも、いかに人気であるかが伺えますね。
設定日
2023年12月12日
構成銘柄
詳細は上述したとおりです。
資産クラス構成
国内株式 94.7%(前回調査時は97.14%)
国内リート 0%(同0.64%)
現金など 5.3%(同2.2%)
手数料
買うとき(購入時手数料):なし
保有時(信託報酬):0.099%
売るとき(信託財産留保額):なし
…コストは激安の信託報酬のみです。
分配方針
決算月は年4回(1・4・7・10月)。
分配金額はファンドがいい感じに決定し、原資が少額の場合は分配しないこともあるようです。
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とし、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、分配を行わない場合があります。また、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
交付目論見書より
販売会社
SBI証券はもちろん、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、の3つで買えます。
→ 新規取り扱いファンド(2025年12月) – マネックス証券
→ 新規取り扱いファンド – 三菱UFJ eスマート証券

NISA適用
成長投資枠のみで購入できます。
つみたて投資枠では、条件を満たしていないので購入できません。
少額積立可能
100円以上1円単位で買付できます。
最低100円からで、101円でも買えるということです。
売却時も100円以上1円単位で発注できます。
まとめ
今回はSBIの欲張りファンドについて、私見とともに紹介しました。
- いわゆる景気敏感株の保有割合が増えた。
- 構成銘柄数は101銘柄(前回95)と増え、まだまだ分散させていく可能性。
- 日銀の利上げによる恩恵を狙って、金融株の動向に期待している。
- 依然として94%が株式でハイリスクよりのファンドなので、買うなら少額積立が無難かも
- ただしベースとなる投資方針は設定から一貫している
構成する資産クラスのほとんどが株式なので、全体としてはハイリスクな商品に分類されるでしょう。
NISAの成長投資枠でしか購入できないことからも推測できます。
魅力的な商品ですが、買い方次第でいくらでもリスク低減を図れるので、ここまで読んでいただいた皆さんが損しないような投資行動を取れることを、心から祈ります。
参考資料
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
月次レポート(2025年10月31日基準)
- いわゆる景気敏感株の保有割合が増えた。
- 構成銘柄数は101銘柄(前回95)と増え、まだまだ分散させていく可能性。
- 日銀の利上げによる恩恵を狙って、金融株の動向に期待している。
- 依然として94%が株式でハイリスクよりのファンドなので、買うなら少額積立が無難かも
- ただしベースとなる投資方針は設定から一貫している
※文中に出てくる具体的な投資商品などは、内容をわかりやすく解説するためだけに用いており、これらの商品への投資を勧めるものではありません。実際に投資するかの判断は自己責任にてお願いします。